汽車は遅れなかった
ようするに、わたしの印象では、戦争が始まったとき、運命がわたしに対して、新しい試練を与えているという感じだったのである。わたしは、そのような運命が、いつかはやってくるだろうとほとんど確信していたので、驚かなかったのだ。
もう、わたしの目のどこかわからないところにいる細菌も、ヴィールスも、先天的な眼球奇形も問題ではなかった。医者たちは、わたしの目の病名については、けっして一致はしなかったのだが……。一億の入間たちをお互いに対立させたのが戦争だった。
この考え方はおかしい、と、わたしも感じている。でも、いまにいたるまでわかっていることは、わたしには自分の準備ができていたということである。そして十月以来待ちつづけ、もう待つことがどうにも耐えられなくなっていたのだった。わたしにはどうしても理解はできなかったのだ。なぜ来るべきものが、やって来ないのかと、わたしは問いつづけていたのだった。
美しい朝が、ミュンヘンと同じように明け、物事は整理され、生活はその平常のコースを取り戻し、この大きなパニックは誤りでしかなかったと、わたしたちに告げていった。
事件のこのような流れは、何かのしるしが、わたしの運命の上に貼られていたことを意味してはいなかったのだろうか?
太陽の光がなま温かくなり、中庭に入りこみ、人形の上にとどまった。わたしたちの部屋の窓がひらき、妻が呼んだ。
「マルセル」
くぎりの短い劇的な声で、相変らずベルギーの放送局からニュースが入ってきた。この声は、今暁一時、メッサーシュミットとストゥーカがベルギー上空に侵入し、いたるところに爆弾の雨を降らしたと告げていた。
ドイツ機甲部隊はアルデンヌまで進撃し、ヘルギー政府はフランスに対して、ベルギー防衛線を助けるよう、正式の要請をしていた。
オランダは、自分たちの手でその防潮堤をひらき、領土の大部分を水浸しにした。そして最悪の場合、アルベルト運河の手前に、侵入者たちを釘づけにすると放送していた。
この間、妻は朝食の用意をし、食卓を整えていた。わたしは陶器のぶつかる音を聞いた。
「なにかニュースあって」
「戦車隊が、ベルギー国境線のいたるところを突破したよ」
「で、それから……」
この日のある瞬間については、わたしの記憶はひじょうに正確なので、こと細かなコンテまで書くことができるだろう。しかし、そのほかの瞬間については、とりわけ、太陽と春の匂いと、わたしの最初の聖体拝受の時の空とまったく似た、真っ青な空を思い出す。
「みんながたつわよ」と、彼女はわたしに告げた。
「どこへ」
「南へよ。どこでもかまわずによ。街のはずれを、屋根にマットレスをつけて通り過ぎる車を何台も見たわ。ベルギーの車がとくに多いけど」
わたしたちは、すでにミュンヘン会談のまえにも、そうした通過に出会っていた。十月に、何人かのベルギー人が、ふたたび、南フランスヘと移っていった。南フランスヘ行くことのできる金持ちたちだった。
「あなたはここに残るつもり」
「よくわからんよ」
わたしは真剣だった。あれほど心待ちにしていた事件がずっと遠くのほうからやってくるのを見たとき、わたしは、まえもっていかなる決定もくださなかった。それは、信号待ちをしているようでもあったし、偶然の運命が、わたしに対してひとつの決定をするのを待ち望んでいたかのようでもあった。
もうわたしに責任はなかった。そこにあるのはおそらく運命という言葉であった。ついさっき説明することを試みた言葉であった。昨夜はまだ、わたしの人生を方向づけるものはわたし自身の手中にあった。わたしのものであり、金を稼ぎ物事が始末されていくようにすべてを処理していくという人生は、わたしの手中にあったのである。
いまはもうそうでない。わたしはわたしの生活が根ざしていたものを失ったばかりだった。わたしはもう、ムーズ河からそれほど遠くないフュメイのかなり新しい街のなかで、ラジオ器具商であったマルセル・フェロンではなかった。人びとの力を超える力によって、その意志のままに流され漂わされていく、何千万の人間のなかの一人だったのである。
もうわたしは、家にも習慣にもとらわれなかった。刻一刻と、空間におけるボールの弾みのようなものが生じてきていた。
このときから、もう決心などというものがわたしを見張ることはなかった。自分の個人的な衝動のかわりに、一種の普遍的な衝動を感じはじめていた。もう自分の生活のリズムで生きてはいなかった。わたしはラジオの、道路の、いつもよりは早く目ざめた街のリズムに侵されていた。
ジョルジュ・シムノン『離愁』一九六一 谷亀利一訳 ハヤカワ文庫 一九七五 16-21ページ
『離愁』(原題は『汽車』)は、奇妙な小説で、引用した冒頭の部分のように、作者自身の告解の生なましい苦渋と、難民列車に乗せられた後のお伽噺めいた夢幻ロマンとが、乱暴に合体させられている。
後者については、論評を避ける。
また、ここに長々と述べられている運命観をあれこれ詮索してみてもつまらない。ここで正当化されているのは、ようするに、シムノンの創作法だ。運命には逆らわないというのは、ナチスの軍事支配が改変してしまった世界および、その影響を作品には描かない、といった諦めと同じだ。大東亜戦争勃発にさいして幾人かの日本人文学者が示した反応とも、よく似ている。
汽車は遅れなかった。
運命を受け入れた時、彼の戦後の選択も決まっていたのだ。
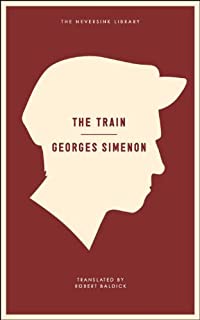
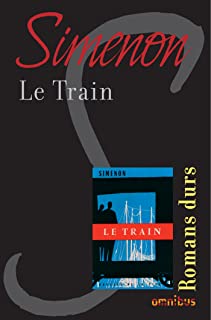
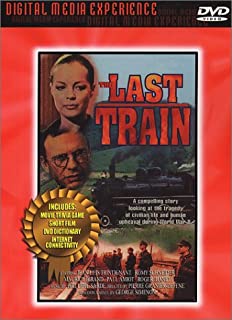


コメントを送信