マルセル・エイメ覚書9
『緑の牝馬』のこと。
La jument verte (緑の牝馬) 1933年
「緑の牝馬」 訳・葉田達治 鱒書房 1956年
エイメの出世作であり、一般的な作者紹介文では、たいていこの作品が解説される。とある農村の濃密な人間模様を描いた自然主義リアリズム小説といえる。
とはいっても、エイメらしい奔放なファンタジー仕様は、最初から全開だ。ともかく、鮮やかな緑色の毛並みの仔馬が生まれ落ちるところから小説ははじまる。舞台は、平穏と退屈とで息もつまりそうな村社会、と通り一遍の記述を記した後、作者は平然と、その村の異様さに筆を転じていく。人口の半分が七〇代以上の老人、しかも百歳代の長老が二十八人もいる。超高齢社会化した地域だ。こうした人口構成であるから、当然の結果というか、順繰りに寿命の尽きる者が相次ぎ、葬儀の途切れるいとまもない。
ファンタジーにふさわしい舞台だが、つづけて語られるのは、老人たちの話ではない。少なくとも、老人たちが次つぎと昇天していく話は、冒頭のみで打ち切られる。
眼に鮮やかな緑の牝馬も、10ページのところで死んでしまう。生前に立派な肖像画を描いてもらっていた。絵は額縁におさまり、主人公一家のしかるべき居間に飾られる。本編がはじまるのは、じつはそこからともいえる。叙述は一般的な客観三人称で進行するが、合間に、この額縁におさまった絵の牝馬の視点による一人称報告体がはさまる。
エイメの描く動物は、だいたい人語を自在に駆使するが、この絵のなかの馬は、小説の半分の語り手をつとめるわけだ。のみならず、主人公一家を四代の七十年にわたって知悉していると大見得をきったり、一転して、「絵になってぺちゃんこになった熱情」を嘆いてみせたりする。ホフマンの『牡猫ムルの人生観』と同工の仕様だ。しかし、この牝馬は牡猫以上の大胆さを示して、村人たちの性生活の秘密にわけいっていく。作者による客観記述が遠慮して踏みこまないで済ませる、人物たちの下半身の秘密を容赦なくあばいていく。村人たちは、この荘厳なる[神の視点]によって標本台にしばりつけられる。
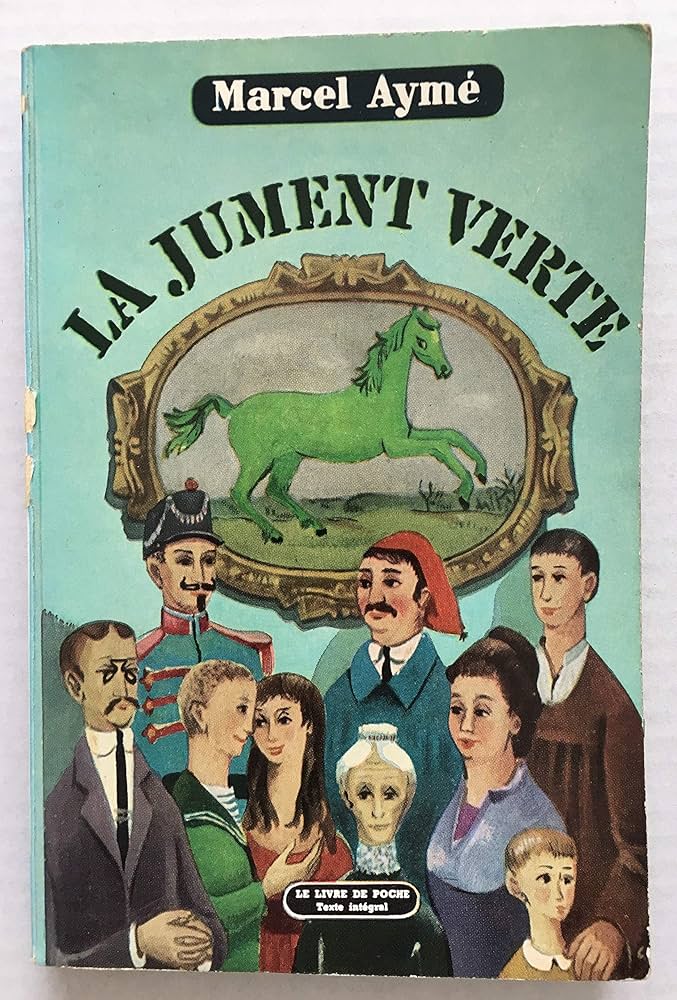
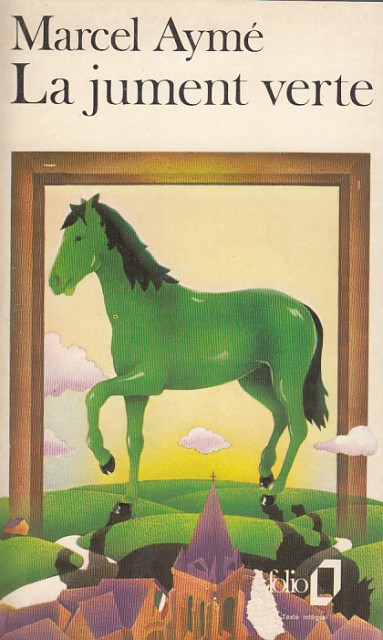
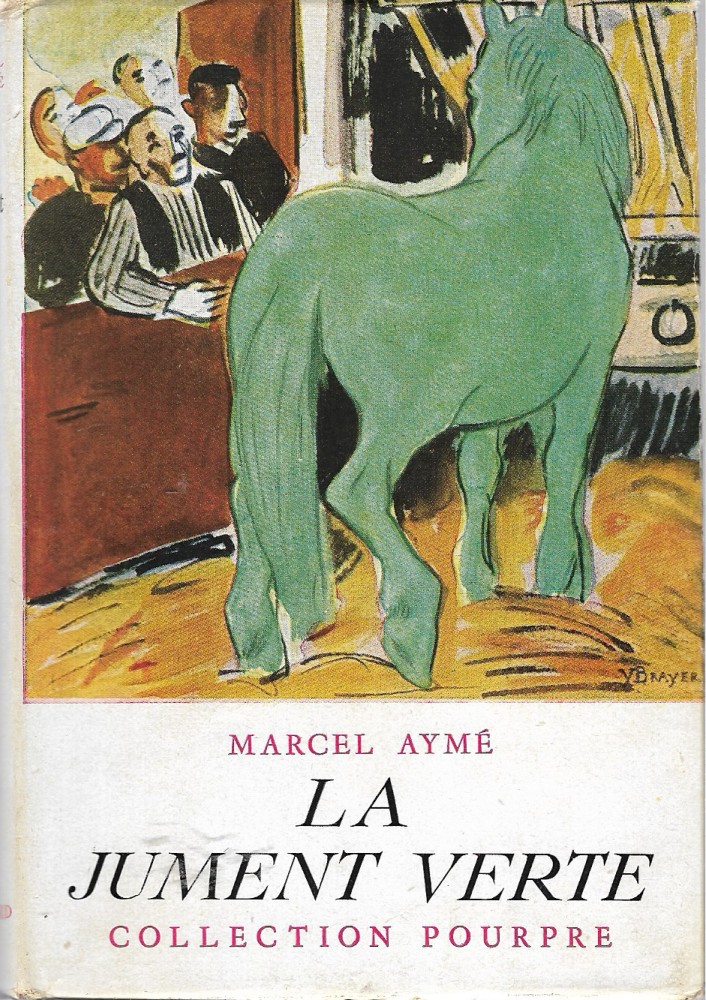
コメントを送信