シムノン&ステーマン序説1
ジョルジュ・シムノンの『死んだギャレ氏』(一九三〇)と、S・A・ステーマンの『三人の中の一人』(一九三二)。
同時期の、ベルギー探偵小説の二作の近縁性は、単に、冒頭の殺人の状況(室内で銃弾で撃たれる)がよく似ているところに限られる。一方は、事件の心理的な解明に深入りしていき、もう一方は、英米仕様のトリック解明の方向をなぞっていく。
『死んだギャレ氏』の被害者は、顔面を撃たれたうえに、ナイフで心臓を刺された。メグレは、パリ近郊だが名前も知らなかった街に派遣される。四五歳、体重一〇〇キロ。単独捜査だ。型通り現場を調べ、殺人捜査の手順には抜かりない。そして、被害者の知られざる素顔。地方まわりのセールスマンという定職は隠れ蓑でしかなかった。妻や息子への質問をとおして、メグレは、被害者が家庭に居場所を持たなかったことを知る。同情、もしくは共感を、おさえられない。
事件の謎はくまなく解明されるが、探偵の事件(被害者)へのシンパシーに関しては未解決のままだ。彼にはペテン師だったという以外に罪はあったのかーーと、探偵は問う。これは、英米流の確立されつつあった探偵小説の原理からは、明確に排除されていった設問だ。合理性にそぐわない。探偵小説では扱えない[謎]だと分別された。シムノンは例外的に、疎外と共感の方向を選び、成功をかちとった。今では、彼の作品に、カミュの実存的寓話、ロス・マクドナルドの詠嘆的ハードボイルドの先駆をみる議論も目新しいものではない。しかし、それを詳細に跡づけても面白みに欠ける。
「フランス式ねじ式」(八月五日の記事)参照。
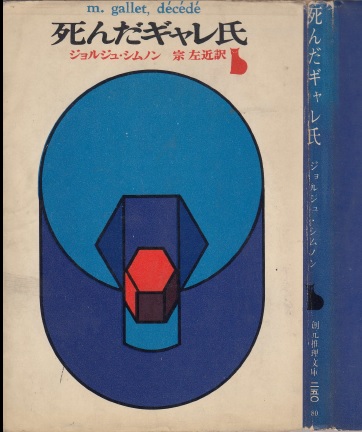
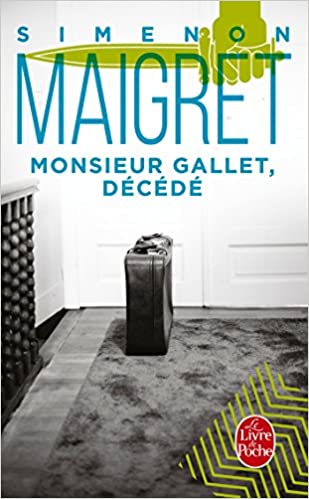

コメントを送信