ソレルの『暴力論』
ジョルジュ・ソレル(一八四七~一九二二)の『暴力論』(一九〇八)は、二つの暴力の歴史哲学を、「革命と戦争の世紀」のために、前奏曲として、挑発的に展開した。
二種の暴力とはーー。《少数者によって支配されるある社会秩序の組織をおしつける》ブルジョア権力〈フォルス〉。そして、《この秩序の破壊を目指す》プロリタリア暴力〈ヴィオランス〉。
『暴力論』の文体は、このよく識られた二分法のように、このうえなく明解な断定と、かなり曖昧模糊とした部分とが混ざり合っている。しかも、後者の多義的ないいまわしは、著者が当時の読者層に向かって意図的に仕掛けた作為(注意深く読まないと、混乱させられる罠)と、著者自身が未錬成な思索を途上のまま投げだしている試論との混合物なので、誤読する要因を雑多にふくんだ、まことに困った[古典]作品なのである。
たとえば、「第六章 暴力の倫理性」には、次のような一連がある。
もし資本家階級が精力的であるならば、彼らは絶えず自己防衛をするその意思を確言するであろう。その率直かつ誠実に反動的な態度は、少なくともプロリタリア暴力〈ヴィオランス〉と同じ程度に、全社会主義の根柢である階級分裂を表示するのに寄与するものである。 (木下半治訳 岩波文庫 一九三三(一九六五改版)下62ページ)
訳者は、この一節の註として、わざわざ、次の一文を記している。《ここの章句がソレル『暴力論』の精髄であるが、同時にそれはブルジョアジーのファシスト独裁に利用され得る点である。》(同 209ページ)
版をかさねた『暴力論』は、少し後のロシア革命に大きな示唆を与え、ロシア的世界革命がヨーロッパにおいて未発に終わった後に台頭した国家社会主義者の枕頭の書にもなった。その相矛盾した事実もまた、よく識られている。ソレルの依拠したサンディカリズムとボリシェヴィキ革命の路線とは隔絶していたにしろ、決定版となった一九二〇年の版に、ソレルは熱烈なレーニン讃歌を書きくわえている。その二年後に、ムッソリーニが史上最初のファシスト国家を出現させた時、ソレルはすでに故人だったが、もし生存していれば「ファシストからの愛」に応えたのかどうか。そんな想像も、いまだにスキャンダラスな話題でありつづけているのかもしれない。
この件での、議論の追跡は、あまりにも面倒な様相を呈している。だから一点のみ確認しておこうーー。ソレルの「プロリタリア暴力〈ヴィオランス〉論」は、二〇世紀を往還して、非暴力抵抗主義のなかに連綿と受け継がれている、と。暴力が非暴力として突出せざるをえないことーーそこにわれわれの、被抑圧者の歴史哲学がありつづける。
ソレルは、フランス革命期の「恐怖時代」に関して、革命裁判の過程において最も多くの血を流し殺戮の人数を増やしたのは、理想主義者、オプティミストだった、といっている。そして、ロベスピエールを例に取り、その理想が自らをギロチン台に送ることになった空転の[逆説]を解明し、翻って、その理想主義が革命の正当な所産であるというよりも、むしろ、宗教裁判や絶対王政から引き継がれた権力〈フォルス〉の負性にほかならなかったことを論証してみせる。ここでの、ソレル用語「権力〈フォルス〉」は、[テロルとしての暴力]といいかえたほうがいいが、そこでまた議論は果てもなく紛糾していくだろう。権力〈フォルス〉とプロリタリア暴力〈ヴィオランス〉ーー。両者の厳密な理論的分類を試みたのは、ファシストのカール・シュミットだった。
再度の逆転は、その後、確認できたろうか。
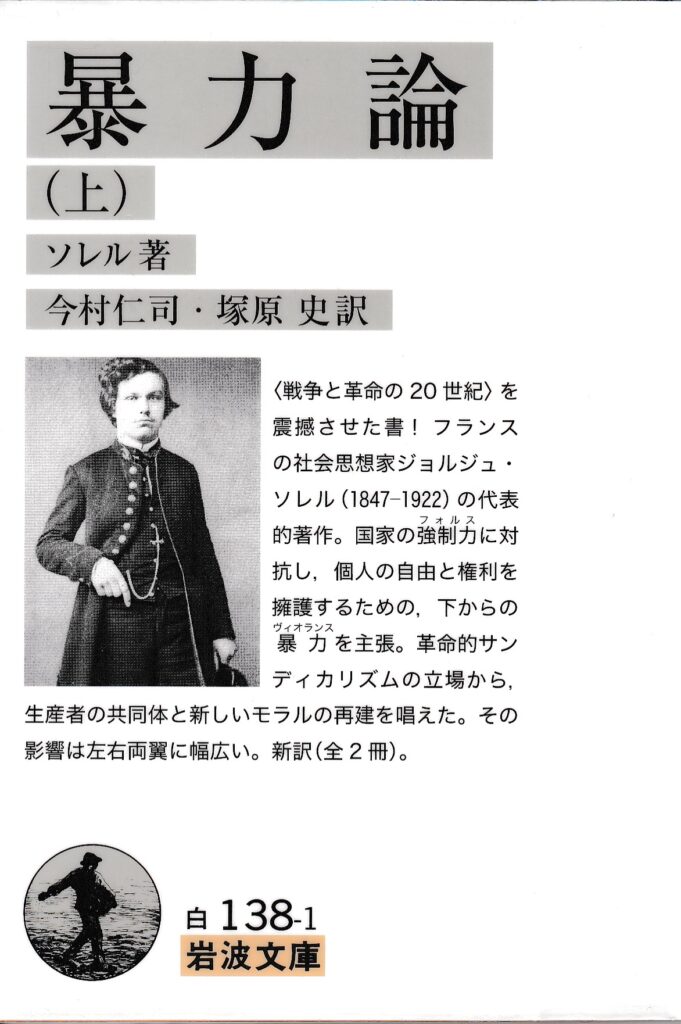
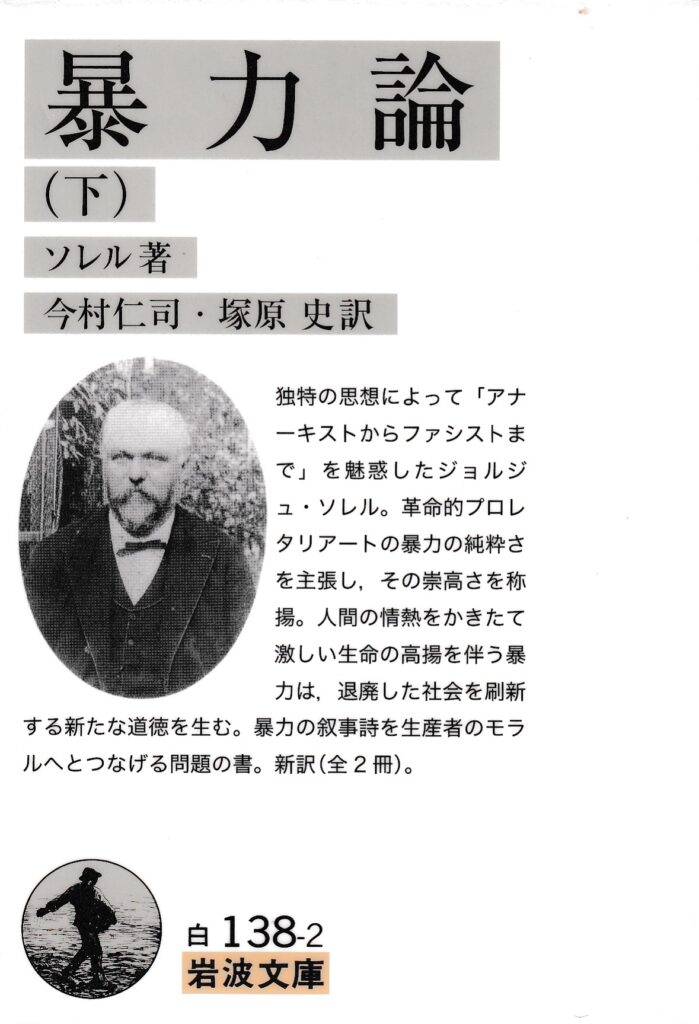
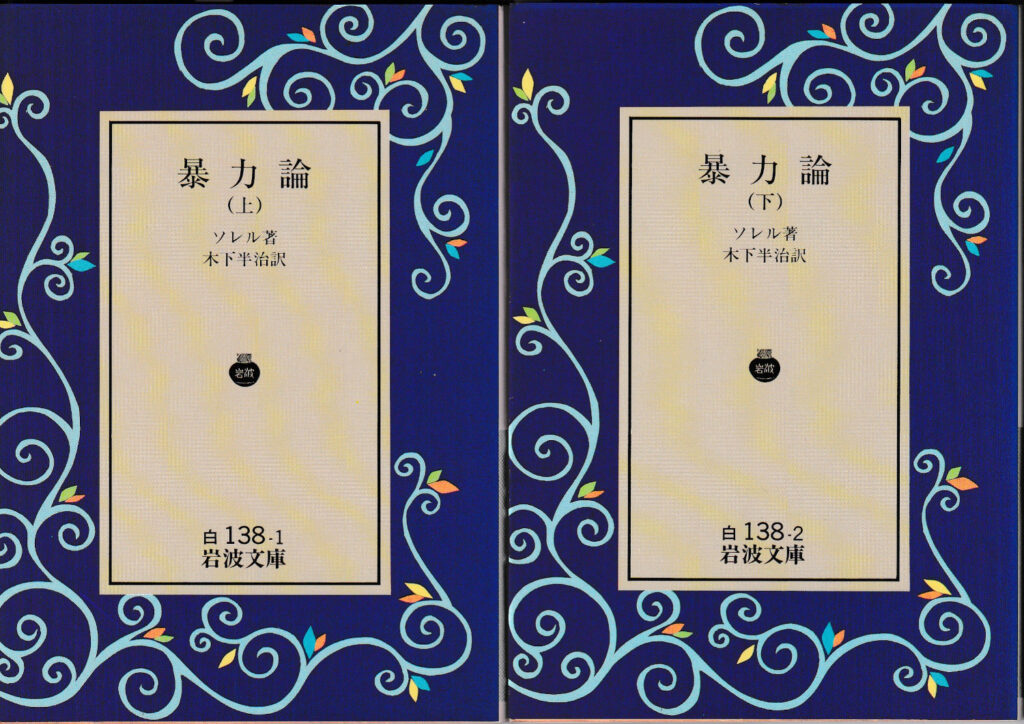
コメントを送信