『アメリカ帝国 グローバル・ヒストリー』
『アメリカ帝国 グローバル・ヒストリー』
A・G・ホプキンズ 2018
ミネルヴァ書房 2025.4
翻訳 菅英輝, 森丈夫, 中嶋啓雄 , 上英明
㊤402p+注137p
㊦276p+注86p 計901p
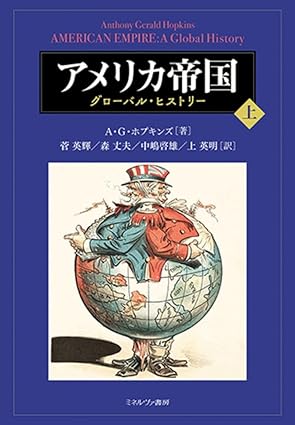
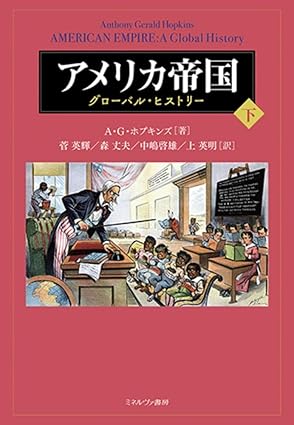
いたるところで「シン帝国主義の時代」の幕開けだなどといった突撃ラッパが吹き荒れている気配。
じつに憂鬱な陥没世界にあって、本書のような浩瀚な帝国主義研究本が出現してくれば、無条件に歓迎したい気分にかたむく。
本書のなかでは、ウィリアム・A・ウィリアムズ『アメリカ外交の悲劇』1959(御茶ノ水書房 1986.7)などは、先行研究として批判的にあつかわれている。
わたしの『北米探偵小説論』(1998年刊の二〇世紀ヴァージョン)では、それらニューレフト史学の主張が、ベースの一部となっていた。
その二一世紀ヴァージョンである『北米探偵小説論21』(2020)で利用したのは、チャルマーズ・ジョンソンやジョン・ダワーの著書だった。執筆時に本書『アメリカ帝国』を手にしていれば、多少は参考にすることが出来ただろう。ただ直接に引用したいような箇所がまったくないことに、読みすすめながら気づく。
比較帝国主義論というのか。著者の周到な「客観主義」を批難する気にはならない。帝国主義に特殊も例外もないこと。アメリカ帝国主義にはアメリカ帝国主義としての一国的な「普遍性」があること。それが歴史的に証明されているわけだ。
そこが、わたしにとっての、第一の収穫であった。
二〇世紀ヴァージョンを書きえたとき、その主要な根拠は、著者にとってアメリカ探偵小説がいかに本質的な「生存の糧」であったかーーそれを証明することにあった。数十年を経て、二一世紀ヴァージョンを用意したとき、その初心を再現することは不可能だった。当たり前というか、一冊の書物は、固有の一回性をもって終わる。同じ試みに挑むわけにはいかない。
否定的にいってしまえば、二一世紀ヴァージョンにあるのは、グローバル世界においてアメリカン・ミステリの優位(個人的な好みにすぎない感覚でも)はすでに色褪せ、どこの国も「同じレベル」だという評価にすぎない。わたしのなかで特権化されていたところの北米探偵小説という原石(野蛮なリアル)は、主観的にであれ客観的にであれ、消滅していたーー。もちろん、それがテーマの根幹ではないから、本の値打ちが下がるということではない。
『アメリカ帝国』から、一点のみ、引用しておく。㊤309p上段
《歴史的な事実を検討すれば、確実に合衆国は一九世紀後半に産業=国民国家を建設することと格闘した後発国のカテゴリーに組み込まれる。》
一九世紀後半という時代において、アメリカは封建後進国日本の鎖国体制解除を強いる帝国主義列強の一角として、アジアに登場してきた。しかし『アメリカ帝国』のこの一節にしたがうなら、列強の一国もその後発性という「条件」にあっては、急速な近代化(帝国主義化)に挑戦しかつ成功した明治帝国と同じカテゴリに分類できる、というのだ。
(この著者が、明治日本や占領期日本について、それほど汎く研究しているとは思えないが、とにかく「明治帝国=三流の帝国主義」といった通念になじんでいたわたしの盲を啓くに充分な見解だった)。
気になったこと。
注に4分の1の分量をさきながら、言及される文献について、邦訳のあるものに案内がない。調べれば済むことなんだがーー。その点数が尠くないので不便を感じる。
著者の博引旁証を愉しむ能力のある読者向きの作りでいいということなのか。
コメントを送信