Rise and Kill First『イスラエル諜報機関暗殺全史』ロネン・バーグマン
『イスラエル諜報機関暗殺全史』Rise and Kill First ロネン・バーグマン(2018) やっと読了。
腰巻の文言をみて、ゲェッーと反吐が出そうになって、しばらく放置していたが、覚悟を決めてとりかかった。一週間以上を費やす。
上下巻1000ページを超える大著とはいえ、時間がかかりすぎ。まず固有名詞が膨大で、丁寧に読まないと、頭からすべり落ちていく。
しかし、読んでも読んでも、果てしない。戦争と暗殺と復讐と謀略の、ネバーエンディングな物語がつづく。イスラエル人の書いた通史としては、客観性のあるものなのだろう。といった判断はさておき、収束のみえないこの「全史」は、まだ途中経過報告だと思える。
原初は建国。これは明らかだが、その前史には、六百万のホロコーストがある。「立ち向かえ、先に殺せ」が、原著のタイトル。必殺の覚悟なしには、第二のホロコーストの犠牲になるしかないーー。これは、イスラエル国家の自己正当化イデオロギー(六百万人という惨禍を無視できる者などいない)と思えていたが。この本の何箇所かには、時の為政者がこの恐怖に理性を喪いかける場面が報告されている。
虐殺の輪廻をはじめたのはナチスだった。かくも長きにわたってその禍根がつづくとは、誰が予想しえたろうか。憎悪の種を撒くのはあまりにも容易だ。百年戦争は、まだまだ流される血の量が足らないといっている。
イスラエルに拠点を置いた暴力は、最初は自衛的な規模のものだったかもしれない。しかし、それは、累進的に膨れ上がっていく。何よりも怖ろしいのは、暴力の物量的な増大ではなく、膨大化にともなう質の劣化だ。暴力は容易に、腐敗していく。それを行使する人間を貶める。人殺しの日常に慣れ、より強烈な刺激を殺人の連続に求めるようになる。腐敗した暴力は、さらに、より腐った暴力を引き寄せる核となる。こうした「歴史」は果てしなく繰り返されつづけてきた。人間がそこから教訓を得ることはあまりに少なく、腐敗にとらわれていく反覆はあまりにも多い。
本書は、半世紀を超える戦争国家の、存亡を賭けつづけた「戦史」を跡づけ、国家規模で避けようもなく腐敗していく暴力の様相を記録した。作者は、とりまとめて、それを「見事な戦術的成功に彩られた、悲惨な戦略的失敗の物語」だといっている。(下352P)
イスラエルの歴史は、冷戦体制からグローバリゼーションに到る「世界システム」が必要とした一種の[平衡装置]だ、と一般的には理解されてきた。終わらない戦争が世界システムの平和を安定させるーーという痛切な背理。だが、それは、一方で、ホロコーストの惨禍から人間がまったく何も学んでいないことの、酸鼻な実例であるかもしれない。
パレスチナによるインティファーダ、あるいは増殖する自爆テロ戦術に関して、歴代のイスラエル政府が、その本質について理解を示していないことは、本書からも明らかだ。
本書のあらゆるページには、「復讐するは我にあり」の祈りが満ちている。祈りがほとんどの場合、卑劣な殺人の正当化に使われてきたとしても、一片の真実をふくむこともまた、疑いえない。そして、民族浄化の犠牲者だった一民族の復讐が、ふたたび新らたな復讐の連鎖の中心となったことも、疑いえない事実だ。
PLOの議長アラファトの死因について、著者は含蓄をもたせて記す。
私がその答えを知っていたとしても、本書に書くことはできないし、答えを知っているということさえ明らかにできない。イスラエルの軍検閲局が私に対して、この問題に関する詮索を禁じているからだ。
(小谷賢監訳 早川書房 二〇二〇 下 275P)
これは、自然死ではない、という断定の、露骨ないいかえ構文だろう。本書で描かれた膨大な事例のいくつかには、こうした検閲との駆け引きがみられるのかもしれないが、それを細かく読み透すに足りる情報量は、こちらにはない。
ただ、現代社会を覆いつくす軍事的暴力の圧倒性に、無力を噛みしめるのみだ。
ーー今日の稿は、『NADS21』「ああ、書いておけば良かった」の項目にも該当する。
①「G・08」以色列探偵小説の報復(1084-87P) 準戦時国家に探偵小説は存在しないという常識論で片づけ、世界最強の諜報機関モサド関連書のタイトルをあげるにとどめているので、修正の必要あり。
②「DD・3・4」(648-651P)プリーモ・レーヴィの、ユダヤ人パルチザンの転戦を描いたフィクション『今でなければいつ』に関しても、若干の加筆が必要だろう。
その二点。
残念度は、★★★★になるか。

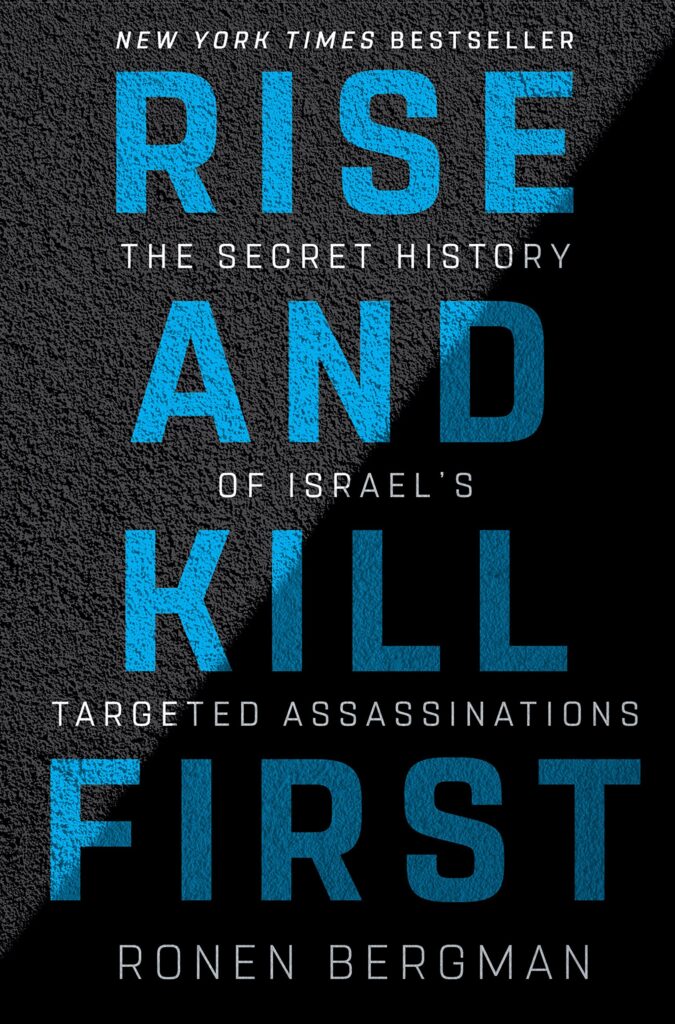
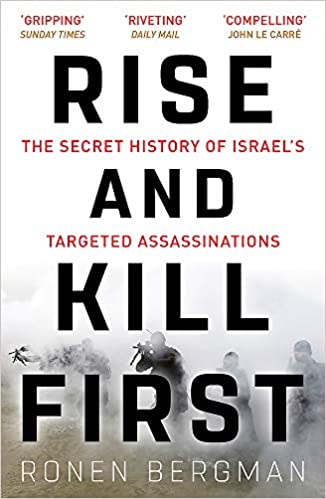

コメントを送信